更新日:2025年1月30日
- 日常生活や学習の支援
- 第3回パラスポーツ教室の報告
- 施設開放の注意事項
- 治療室の利用
- パイロットコーポレーションからの贈り物
- 視覚障害について
- 地域センター公開研修会
- 夏季教育相談会
- ご理解・ご協力のお願い
- 「HIRATSUKA FAN PROJECT:ART」紹介パネル展示
- 地域の方の学校見学
- 湘南ベルマーレ主催イベント「みんなのたのしめてるか。」に参加しました
- 学齢期の児童生徒の教育相談
- 湘南ベルマーレ応援給食
- 視覚補助機器展示会
- 乳幼児教育相談を更新しました。
- 視覚障害スポーツ体験会
- 平塚合同庁舎での学校紹介
- 夏季教育相談会
- 地域センター公開研修会
- トヨタモビリティ神奈川平塚四之宮店での作品展示
- 湘南ベルマーレ主催イベント「みんなのたのしめてるか。」に参加しました
- 施設開放について
- 地域のイベント・作品展示
ここから本文です。
学齢期の児童生徒の教育相談
こんなことはありませんか?
「子どもの目の見え方が心配…」
「小学校に通っているが、黒板の字が見えにくいようです。」
「視覚に関する支援が必要な児童のための教材・教具が知りたいです。」
「近づいて見るので、読む姿勢が悪くなっています。」
「読み間違え・書き間違えが多くて、気になります。」
「文字の大きさは、どれくらいがいいのでしょうか。」
「近づいてくるボールに気が付かないようです。」
「ずいぶん、まぶしがります。」
平塚盲学校は、ご相談を受け付けています
- 見え方に関する支援が必要な児童生徒やその保護者、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校等の先生等、どなたでも相談することができます。
- 必要に応じて他の教育機関や医療機関、県内の視覚障害関係諸機関などと連携して、相談を行います。
- 相談に関する費用はかかりません。
- 教育相談は本校への転入学を前提とはしておりませんので、まずはお気軽にご相談ください。
- 研修の講師も行います。
相談方法
(1)電話による相談
お電話をいただきましたら、担当者がお話を伺い、今後の支援方法などを一緒に考えていきます。
(2)来校による相談
- 来校前に電話での連絡をお願いします。担当者と日程を調整し、平塚盲学校に来校していただいて、直接お話を伺います。
- お子様が一緒に来校される場合は、保護者の方が相談をしている間、お子様は別の担当者と遊びや学習などに取り組むこともあります。
- 必要に応じて、学校の見学を行ったり、学校にあるルーペ・単眼鏡・拡大読書器や教材・教具などを紹介したりすることも可能です。
- 学校及び関係機関の方からの来校相談も受け付けています。
(3)学校などへ訪問しての相談
学校などから依頼があった際には、訪問して相談を行います。授業等見せて頂いた後にケース会議を行います。
~見えにくさへの支援6.~
★盲導犬とともに
ある日のことでした。通勤途中の公園で、時々見かける盲導犬を連れた方が、立ち止まっているところに出くわしました。パートナーの盲導犬とのやり取りが聞こえてきたのですが、どうやら、公園内のルートを見失い、小道に入り込んでしまったようでした。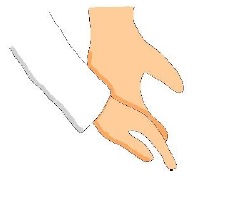
そこで、「どうされましたか?ガイドしましょうか?」と声をかけると、援助依頼があったので、ハーネスを握っていない右手の甲に、そっとこちらの手首辺りを触れ、私の肘辺りを握ってもらいました。そして、どちらに向かうか確認しながら移動をしました。
その方は、小道からいつものルートに入るところにある木をランドマーク(目印)にしていたようなので、そこまでガイドをしました。その方はいつものルートに出られて安心され、感謝の言葉とともに、実は新しいパートナーの盲導犬を迎えて、まだ十分にルートが分かっていなかったようだとのお話をされ、その場は別れました。
そして、その次の日のことです。偶然、またその方を公園の入り口でお見かけしました。私は迷ったのですが、心配だったので、立ち止まってその方が昨日ルートを外れてしまったところをパートナーとともにクリアできるか遠目で見届けました。
目印の大きな木まであともうほんの少し来たところで、その方は右手で辺りを探ります。私は「あと少し右!」と心で唱えました。そして、その方はなんとかランドマークの木に触れることができ、安心したように、これだよ!とパートナーと繰り返し確認し、いつものルートを歩いていかれました。
★盲導犬を見かけたら
盲導犬はペットではなく、大切なパートナーです。大切な仕事をしている最中なので、かわいらしいからと言って、次のようなことは絶対にしてはいけません。
盲導犬に声をかけたり、じっと前から見たり、口笛をならしたりしない。
盲導犬に食べ物を見せたり、あげたりしない。
盲導犬をなでたり、ハーネスを触ったりしない。
自分のペットとあいさつさせようと近づけたりしない
以上、公益財団法人日本盲導犬協会HPより
盲導犬に限らず、白杖(はくじょう)を利用する視覚障害者を見かけたときは、「盲導犬がいるから大丈夫だろう。」などと思わずに、何か困っていることないかな、と気にかけてください。そして、危険な方向に進もうとしていると感じたら、「盲導犬の方(白杖の方)止まってください。」と迷わずに声をかけてください。視覚障害者が駅のホームから線路に転落してしまう痛ましい事故がいまだにあります。声をかけることは勇気のいることですが、その勇気には感謝とお互いの安心感という大きな見返りもあることでしょう。
お問い合せ
0463-31-1341(職員室)
相談支援担当
バックナンバー
<見えにくさへの支援1.>(PDF:144KB)
<見えにくさへの支援2.>(PDF:144KB)
援助依頼について
<見えにくさへの支援3.>(PDF:127KB)
保護者が支援するために、保護者を支援すること
<見えにくさへの支援4.>(PDF:188KB)
見えにくさは人それぞれ、活用する支援の方法も人それぞれ
<見えにくさへの支援5.>(PDF:214KB)
見えにくさに配慮した校内環境を整える
